鬼族の代表が、ギルドの師弟に加入して、数週間がたった。
その間、鬼族たちが協力して作業を行い、木造の学校の建築、木造の宿泊施設の建設、食堂の建設を行なった。
ルドウィンも協力して、ある程度使えるクオリティにまで仕上げた。
しかし、やはりこれ以上のクオリティで作りたいなら、専門的な技能が必要なので、ギルドの加入が必須になる。
そんなことを考えながら完成した木造建築物を眺めていると、鬼族がルドウィンを呼んできた。
「ルドウィン殿、領主の使用人が呼んでいます!」
「わかった。今行く。」
おそらく、鬼族代表がギルドの師弟に入った結果を伝えにきたんだ。
ルドウィンは、緊張でドキドキする心臓を抑えながら、使用人のところへ行った。
「領主様がお呼びです。屋敷にお越しください。」
「わかった。」
ルドウィンは使用人と共に屋敷に向かった。
舟の上にいる時、ドクドクと心臓の鼓動が鳴っていた。
屋敷に着き、大広間から、2階に上がり、領主の部屋の前に言った。
使用人が領主の部屋をノックする。
「領主様。ルドウィン様がお見えです。」
「入れ。」
使用人がドアを開けた。
ルドウィンは部屋に入り、領主を見た。
領主は、じっとこちらを見つめ、真剣な表情をしている。
ルドウィンはごくりと唾を飲み込み、領主の言葉を待った。
「君が遣わした鬼族に関してだが……、」
「……いかがでしたか?」
ルドウィンは、心臓がこれまでにないほどドキドキしている。それもそのはず、自分の命がかかっているのだから。
「最初は、馴染むのに時間がかかったらしいが、熟練職人が素晴らしい人材だと褒めておった。」
「!」
ルドウィンは喜んだ。思わず声が出そうになったが、それは我慢した。
「全く、信じられんよ。あんな凶暴な鬼族を、こんなに手懐けて……。天晴れだ。この調子でどんどん各ギルドに加入させて良いぞ!」
「恐縮でございます。では、早速戻って数人、候補者を派遣します。」
「よろしく頼むぞ。」
領主はとても上機嫌になった。
よっぽど評判が良かったのだろう。
また、これがうまくいけば、他の領主よりも地位が高くなる可能性がある。
だから、領主は満面の笑みを浮かべていた。
「用がないなら、もう行って良いぞ。」
「では、1点お願いがあります。」
「なんだ。行ってみろ。」
「はっ。ギルドは通常、住み込みで見習いをすると思いますが、1週間のうち、何日かは島に戻らせて欲しいのです。その代わり、代わりの人材を派遣します。というのも、鬼族の島では人材が足りていませんから。」
「良いぞ、好きにせい。」
「ありがとうございます。」
「他にあるか?ないなら戻って良いぞ。」
「はっ、失礼致します。」
ルドウィンはお辞儀をして、部屋をでて、屋敷から出た。
そして、鬼族の住処の島へと向かった。
「どうでした?」
鬼族たちが心配そうにルドウィンの言葉を待った。
「ああ。大丈夫だった。」
「良かった!」
鬼族たちは安堵の表情を浮かべ、ホッと肩を撫で下ろした。
「追加で各ギルドに派遣する鬼族が必要だ!誰か、ギルドに行って来てくれないか?これも現状を改善するためだ!頼む!!」
ルドウィンがそう言うと「今度は自分も。」と、以前よりも多くの人が、ギルドに行っても良いと、名乗りをあげた。
「ありがとう、みんな!」
ルドウィンは鬼族たちに頭を深々と下げた。
その後、手を上げてくれた鬼族、一人ひとりと話をして、各ギルドに振り分けて、街のギルドに行ってもらった。
ルドウィンは鬼族たちを見送った後、やるべきことがあった。
そう、今さっきできたばかりの学校の開校だ。
子供達を教育しなければならない。もちろん、大人でも学べるようにする。
昼は子供向けに開校し、夜も大人が学べるように開校する。
そういうわけで、残った鬼族たちを集め、学校の説明会を開いた。
「みんな。聞いてくれ。学校を開く。」
「学校?」
「勉強するところだ。子どもはもちろん、大人でも学べる場だ。」
「どう言ったことを勉強するの?」
「主に簡単な算数、そして文字の読み書き。最初のうちはこのくらいだ。後々段々高度なことを学習してもらう。」
「へえ!」
子供達がキラキラ目を輝かしてルドウィンの言葉を聞いている。
今まで、鬼族の子供たちは遊ぶことしかしなかったのだろう。
勉強という新しいジャンルのことができるので、ワクワクしているようだ。
また、大人たちも興味津々だ。
大人たちも、算数や文字の読み書きはできない。言葉を話すことはできるが、文章を書くことができないのだ。
ルドウィンは、文章が書ける人が多くなることで、本を書いてもらい、文化レベルを上げれたらなと思っている。
また、算数ができる人が多くなることで、後々行う経済活動もしやすくなる算段だ。
「質問はあるか?」
ルドウィンがそういうとたくさんの手が上がった。質問の内容は、開校は何時から何時までかとか、お昼はどうするのかとか、勉強道具はどうするかとか、おやつはあるかとかだ。
具体的な話はあまり考えていなかったので、質問を答えながら、決めていった。
いよいよ、質問の回答が終わり、学校を開校することになった。
校長はもちろんルドウィン。
そして、先生はルーナ、リリアリー、ティルシーだ。
生徒は鬼族の子供や大人、そしてイアだ。
ルーナは文字の読み書きや算数の先生だ。
ルーナは文字が上手で、綺麗な字で見本に最適だ。
ちなみに、この世界には紙なんて上等なものはなく、みんなワックスタブレットに、スタイラスを使って文字を書いた。
ワックスタブレットは木の板にワックスを薄く塗ったもので、スタイラスは一方は先が尖っており、もう一方は先が平たくなっている棒だ。
ワックスタブレットをスタイラスで引っ掻いて文字を書くことができる。そして、平たくなっているところで文字を消すことができる。
算数もしっかり教えられる。
ルーナは子供の頃から、家庭教師を雇い、学んでいたそうだ。
だから、教え方も上手だった。
リリアリーは体育の先生だ。
リリアリーは体力抜群で、運動神経も良い。
鬼族の身体能力と比べても桁が違う。
なので、鬼族に体育を教えられるのだ。
また、この体育の授業内容は桁違いのすごさで、ルドウィンの世界の常識とは違う。
例えば、島を何周も回ったり、数十メートル立ち幅跳びしたり、大木を使った剣の稽古など。もはやビックリ人間大会だ。
だが、思いっきり体を動かせて、鬼族たちは楽しそうだった。
ティルシーは狩りの先生だ。
ティルシーは自分の食糧を調達するために、弓矢での狩りの腕前をメキメキ上げ、もはや達人のレベルになった。
ただ、教えるのは絶望的に下手くそで、「ここで、バビュ、そしてすかさずドシャっていう風に……」というふうな、オノマトペで直感的に教えている。
ルドウィンは全くわからなかったが、しかし、意外にも鬼族たちには好評だった。
鬼族も直感的で、野生的に生きていたのだろう。
鬼族は、ティルシーと通じるものがあるようだ。
こうして、ルドウィンたちが学校の先生となり、鬼族たちにありとあらゆることを教えて行った。
ルドウィンたちは学校の先生として仕事をして、鬼族たちは、食糧を調達する班、授業を受ける班、畑作業をする班、畑を広げる班、建物を増築する班に分かれて、輪番制に作業を行なった。
数週間が経つと、各ギルドで学習していた鬼族たちも加わり、さらに作業が捗った。
学校では、最初はルドウィンたちだけだった先生も、学習が進んでいる生徒が先生になり、最終的には、各ギルドで学習した鬼族たちが先生になった。
そうしているうちに、建物のクオリティが上がり、灌漑施設のクオリティが上がり、土地の改良などが進んでいった。
そして、最初植えた小麦や大麦が収穫できるほどに育った。
ルドウィンは、早速鬼族たちに指示し、小麦や大麦を収穫した。
豊作だ。
半分は領主に収めないといけないが、それでもしばらくは食べ物に困ることはないだろう。
しかも、あれから木を伐採し、畑を広げ、小麦や大麦、じゃがいもなど、多くの農作物を植えた。
それらも近々収穫できそうなので、食べ物の心配はなさそうだ。狩りや採集でも調達できているのも安心材料だ。
だから……記念すべき初収穫の日を祝って、パーティーを開くことにした。
鬼族の女性たち、ルーナ、イアが料理をし、リリアリー、ティルシー、鬼族の男たちが食材を調達する。
その様子を、ルドウィンが見ていると、鬼族頭領が話しかけてきた。
「ルドウィン殿、少し時間よいか?」
「どうした?何かあったか?」
ルドウィンが鬼族頭領に尋ねた。
「いえ、何もないが、少し、勉強の質問をしてもいいか?」
「勉強の質問?」
ルドウィンはちょっと意外だった。
「そうだ。実は、一族たちのために何かできることがないかと考えた結果、猛勉強を始めた。それで、わからないことがたくさん出てきて……すまないが、もし今時間が空いていれば、学習の手伝いをしてくれないか?」
「そうか。」
鬼族頭領もきっと、いっぱい悩んだ結果、慣れない学習をすることになったんだろう。
頭領なりに、一族たちのために一生懸命役に立とうとしている。
素晴らしいことだ。
「もちろん。喜んで手伝おう。何がわからないんだ?」
「ありがとう。まず……」
こうして、ルドウィンは頭領の勉強を手伝った。
異世界の文字の読み書きは、まだルドウィンは教えられるレベルではなかったので、ルーナを呼んで、文字の読み書きはルーナ、算数はルドウィン、その他、経済学や異世界(ルドウィンのいた世界)の歴史についてはルドウィンが、頭領に教えた。
頭領は今までかなり勉強をしてきたのだろう。
良い質問ばかりだった。
だから、教える方も、ついつい熱が入ってしまう。
ルドウィンとルーナが、数時間、頭領に夢中で勉強を教えて、頭領が懸命に勉強していると、リリアリーがルドウィンたちを呼んできた。
「ルドウィン、ルーナ、頭領、ご飯ができましたよ。」
「わかった、今行く。」
ルドウィンたちはキリの良いところまで学習して、学習を終え、みんなが待つ食堂へと向かった。
すると、そこに並べられている食べ物は、とても美味しそうなものばかりだった。
今回大豊作だった大麦や小麦を使った料理や、狩りや採集で得た食材を使った料理が並んでいる。
パン、麦ご飯、きのこパスタに、きのこシチュー、きのこピザ、ケーキや、ホットケーキ、魚のフライや、とんかつ、サラダ、きのこのソテー、猪のステーキなどが、木のお皿に綺麗に盛り付けられている。
また、一人一人の木のコップに、ビールが注がれている。
ちなみにビールは作るのに時間がかかるので、今回収穫した大麦は使われておらず、おそらく市場で購入したものだろう。
あまりに美味しそうでお腹がなってしまった。
ルドウィンがビールのコップを取ると、ルドウィンたちを待っていたみんながコップを取った。
「みんなありがとう!おかげでこんなに美味しそうなご飯にありつける!さあ、今回は記念すべき初収穫の祝いの日だ!みんな日々頑張る自分を労って今回は存分に飲んで、食べてくれ!乾杯!」
「乾杯!!」
みんなの木のコップが当たり、カコンと鳴った。
ゴクゴクとビールを飲む。
勉強を数時間教えて、カラカラの喉が、ビールで潤う。
すごく、美味しかった。
そして、ご飯。
ビールが塩気のあるご飯をより美味しくした。
ルドウィンが好きなご飯ばかりで、どれを食べるか迷ってしまう。
魚のフライとトンカツは、ビールと合う最高の味だった。
猪の肉とも合う。猪の肉は、豚肉によく似ていた。
それもそのはず、猪が家畜化したのが豚だからだ。
やはり、自分たちが作った農作物から作られているご飯は、格別だった。
ルドウィンはそのとても美味しいご飯に舌鼓をしながら、周りの光景にも目を配った。
みんな自分の好きな会話を、自分の好きな人たちとしながら、おいしいご飯を楽しんでいる。
ルーナは文字や算数の先生をしていたこともあり、鬼族の子供達や大人たちに文字や算数についての質問攻めにあっていた。
ルーナはその質問に対し、1人1人丁寧に答えている。
それを、鬼族たちは真剣にウンウンと頷きながら聞き、勉強している。
リリアリーは鬼族の子供や、大人たちと、効率の良い筋トレの話や、武勇伝の話をしながら盛り上がっていた。
リリアリーが武勇伝の話をすると、おおーと鬼族たちの歓声が上がる。
あの鬼族たちが驚くのだから、きっととんでもない武勇伝なのだろう。
ルドウィンも武勇伝の内容にちょっと興味があった。
ティルシーは前回のパーティーは食べ物に夢中だったが、今回は鬼族たちと狩りの話で盛り上がっていた。
特に、ティルシーは鬼族たちの子供たちに人気で、直感的な教え方が好評だった。
ティルシーはそれに喜んだのか、食べ物にも時々手を出すが、狩りのコツの話を鬼族たちと楽しそうに話していた。
イアも、鬼族たちの子供達と共に、ルーナ先生の話を真剣に聞いて、勉強している。
イアは文字の読み書きはできるが、どうも算数が苦手らしい。
だから、算数を集中的に学習していた。
みんな勉強熱心だ。
パーティーの時まで勉強をするなんて。
きっと、今まで勉強をしたこともなく、今まで押さえ込まれていた知の欲求が、溢れ出てきたのだろう。
ルドウィンは、鬼族に素晴らしい可能性があると感じていた。
適切な学習をすれば、どんどん知識を身につけるだろう。
将来が楽しみだ。
そして、みんなが楽しそうにご飯を食べながら夢中で学ぶ姿は、ルドウィンにとって、幸福な光景だった。
「頭領、聞いてくれ。」
「ルドウィン殿。何だ?」
ルドウィンはその光景を目に焼き付けながら、鬼族頭領に話しかけた。
「頭領が前、こう言っていたのを覚えているか?『みんなが豊かになれる世界。そんな世界を俺が生きているうちに見てみたいものだ。』と。」
「ああ。はっきりと覚えているし、その気持ちは今も変わらない。」
ルドウィンは、固い決意と共に、こう言った。
「俺が見せてやる。みんなが学べて、豊かになれる世界、理想郷の世界を。この世界に無いなら、俺がこの手で作ってやる。」
「……ああ。」
ルドウィンがこう言うと、鬼族頭領は嬉しそうに鋭い牙を見せながら笑顔を見せた。
「その言葉を聞いて、将来がとても楽しみになった。ありがとう。」
ルドウィンも鬼族頭領に微笑むと、グイッとビールを飲んだ。
その時のビールの味は、いまだかつて味わったことのないほど、うまい味だった。
ルドウィンと鬼族頭領は、パーティーが終わるまで、この幸せな景色を、ずっと見守っていた。
理想郷に少しずつだが、近づいている。
だが、まだまだ俺の知る理想郷までは、道のりが遠い。
しかし、今できることを精一杯やれば、この仲間たちとなら、理想郷を作り出せる。
ルドウィンはそう思った。
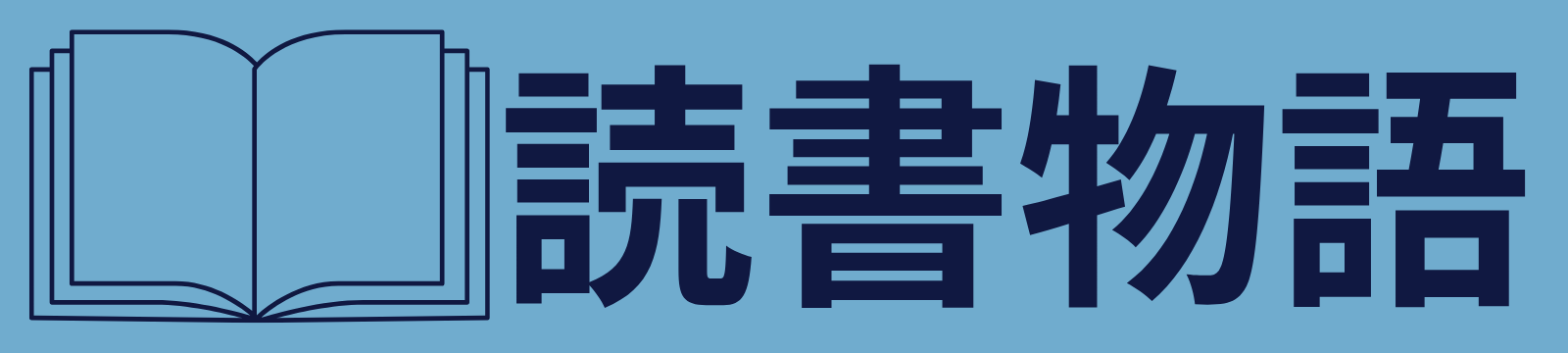









コメント