ルドウィンは発展した鬼族の島を見てまわった。
鬼族だけでなく、商売や仕事のために来たのだろう、他の地域の人間達も大勢、忙しく働いていた。鬼族が少なく思えるほど、他の地域の人間の数は多かった。
たくさんの市場が開かれ、さまざまなものが売られていた。
りんご飴、アップルパイや果物のジュース、果物、野菜、肉、魚、生活用品や、服、防具、剣、金や銀で作られた食器、アクセサリーなどなど。
どれも魅力的で目移りしてしまう。
ルドウィンはりんご飴を買い、りんご飴を舐めながら街を歩いた。
ちなみに、ルドウィンは変装をしている。
なぜならば、ルドウィンは正体がバレると、人だかりができるほど人気者だからだ。
ルドウィン王は鬼族にとって富をもたらしたもの。救世主らしい。ルドウィンを崇める宗教もできてしまうほどだ。ーーそれは規制しなければなーーとにかく、正体がバレると鬼族は仕事どころではなくなるため、ルドウィンは変装して街を歩いた。
つけ髭、ウィッグをつけ、服装も王が着ているとは思えないほど、普通な格好をした。
というわけで、ルドウィンが街を歩いても、誰も声をかけなかったし、誰もルドウィンだということに気づかなかった。
ルドウィンは、この時間を利用し、ルーナ、リリアリー、ティルシー、イア、鬼族頭領の元を訪ねることにした。
今まで、ルドウィンは国王の仕事を全うするため、仲間にお金を与え、自由行動をしてもらっていた。
だが、自由な時間ができた今、気の許せる仲間に会いたくなって、訪ねることにしたのだ。
まず、ルーナに会いに行こう。
そこらにいる鬼族にルーナの居場所を尋ねる。
どうやらルーナは塾の先生になっているらしい。その塾を訪ねた。
街中の良い立地に、立派な塾があった。
ルーナ塾。そう看板に書かれていた。
塾に入ると、そこにはたくさんの塾生で賑わっていた。
教室に入ると、いた。ルーナが生徒に教えている。
ルドウィンはルーナの授業を終えるまで近くの休憩室で待つことにした。
休憩室には、木製のクーラーボックスがあり、そこに飲み物が冷やされているようだ。食べ物やジュースの屋台もある。ソファやベット、テーブルも常備されている。さすが、人気のあるルーナの塾だ。設備が充実している。
その設備を使って、勉強熱心に休憩時間も本を読んでいる人や、勉強のことを話している人、休憩時間の本来の目的である、休憩をする人もいる。飲食をしたり、雑談をしたり、仮眠を取ったり、各々、さまざまな休憩の取り方をしている。
ルドウィンは休憩室にいる塾生達を眺めながら、過ごしていると、チャイムが鳴ったので、慌ててルーナが担当していた教室に行き、教科書や余ったプリントを片付けして職員室に帰ろうとしているルーナを捕まえた。
「ルーナ、久しぶり。」
「え?どなたですか?……まさか、その声はルドウィンさん?」
「しっ!バレると厄介なんだから!」
「あっ、そうですよね。すみません。」
そんなやりとりをし、ルドウィンはルーナと話した。
仲間が今何をしているかわかるかと聞くと、イアなら塾で勉強をしていると言ったので、イアを呼んできてもらい、休憩室に入り、3人で久しぶりに話した。
ルーナは今まで、子供の鬼族達に教えるために、勉強をたくさんしてきたらしい。
鬼族達は勤勉な人が多く、子供も、飲み込みが早く、勉強のスピードも速い。
だから、そんな優秀な生徒の質問に答えるために、先生である自分も、必死に勉強したらしい。
その勉強に使った教材も、鬼族の専門家が書いた本だというので、これからも鬼族の勤勉さがわかる。
イアは今までルーナの教室に通い、たくさん勉強をしていたらしい。
昼は学校、夕は塾や図書館で勉強漬けの毎日を過ごしている。
知らないことがたくさんあって、毎日勉強するのが楽しいらしい。
ちなみに、ルーナと一緒に暮らしていて、ルーナが食事の面倒は見てくれているようだった。
ルドウィンは、ルーナの仕事とイアの勉強の邪魔をしたら悪いので、もっと話したかったが、ルーナとイアとは別れ、次の仲間のところに向かうことにした。
次はリリアリーだ。
鬼族に場所を聞き、リリアリーがいる場所を訪ねる。
どうやらリリアリーは、剣術の先生になっているらしい。
その場所に行くと、看板があり、立派な道場があった。
「リリアリー剣術道場」とある。
道場の門下生が、剣道の稽古をしていた。
竹刀を持ち、防具を身につけ、試合をしている。
リリアリーがそれをみて、アドバイスを逐一している。
ルドウィンは試合が終わり、ひと段落つくまで、試合を興味深そうに見ながら待った。
試合は、畳の上で行われ、複数のブロックに分かれて対戦している。
複数の試合を、リリアリーが見て回りながら、的確に教えているのだ。
周りに門下生が立ち、見守っている。真剣にメモをしている鬼族もいる。
そして、肝心の試合だが、とてつもなくハイレベルだった。
ルドウィンが昔いた世界でも剣道はあったが、目視できないほど、速く竹刀が動いているのは見たことがない。
また、その素早い攻撃をおそらく竹刀で防いでいるのだが(そもそも試合に出ている鬼族が素早すぎて目に見えないため、予想するしかない。)一撃一撃がとんでもない音と風圧で、離れて見ている人にも届き、凄まじかった。
「そこの観客!」
突然ルドウィンの方を指差した。その人物が、ルドウィンだとわかっていないようで、ただの見物しにきた人間の客だと思っているらしい。
「時々、竹刀の破片が高速で飛んでくるから、危ないので出て行ったほうが良い。」
ルドウィンはその言葉を聞いてゾッとした。
どんな試合だよ。
ルドウィンは命懸けの試合観戦をビクビクしながら過ごし、やっと試合が終了した。
なので、次の試合を始めようとしているリリアリーを捕まえた。
「リリアリー、ちょっと待ってくれ、少し時間をくれないか?」
「ん?この懐かしい声は……まさかルドウィン殿か!」
「しっ!すまないがバレると面倒なことになるから、内密に……。」
「ああ。そうだったな。承知した。」
リリアリーは小声でそう言った。
リリアリーは他の師範代に指導を任せ、少し休憩を取ると言って、ルドウィンと街中を歩きながら、話した。
「ん〜!久しぶりに外に出るな!外はお天道様が気持ちいいな!」
リリアリーが太陽を浴び、気持ちよさそうに腕を伸ばして、背伸びをして、そう言った。
リリアリーはずっと道場にこもって、ほぼ休まず指導をしていたらしい。
とんでもなくストイックだ。
そして、エネルギッシュだ。
「リリアリー、ありがたいが、無理はするなよ。体を壊したら困ってしまう。」
「心配してくれるのか?」
リリアリーはキョトンとした顔でルドウィンを見てくる。
心配されることは、今までなかったのだろう。新鮮な感情を感じているようだ。
「ありがとう。だが、大丈夫だ。私の体はとても丈夫だ。今まで風邪一つひいたことがない。ちょっと無理した程度ではビクともしないぞ!」
それを聞いて安心した。
だが、数ヶ月ぶっ続けで道場にこもって稽古するのは、ちょっとの無理だとは思わないが。
ルドウィンは久しぶりに、色々規格外のリリアリーと話して、楽しかった。
「ちなみに、ティルシーは何をしているかわかるか?」
「ティルシー?ああ。有名だぞ。あの城で先生をしている。」
リリアリーが指を指す。そこには、島で一番良い立地に、大きなお城に広い森が隣接している。
気にはなっていたが、まさかティルシーが働く場所だとは思わなかった。
「それで、話は変わるが、ルドウィン殿の話も聞かせてくれ。一体どうやってこの知識を身につけたんだ?だって、ルドウィン殿のいうとおりにすると、みるみる豊かになっていくんだもの。しかも、「刀」という最強の武器のコンセプトまで知っていて。いくら先進国である天界でも、ここまで様々なジャンルのノウハウを知っている偉人はいなかったと思うが。」
「ああ。」
ルドウィンは回答に困った。
リリアリーもルーナと同じような質問をしてきた。
それもそうだろう。これらの技術はこの世界の文明レベルにはなかった、オーバーテクノロジーなのだから。
だが、「俺が異世界から転生した」と、本当のことを言うのは、正直怖い。
今まで仲間がルドウィンを慕ってくれるのは、ルドウィンが火の国連合、火の国の王国の右腕、ルドウィンだからだろう。
つまり、上司だから、部下は従っているのだ。
これが、ルドウィンがただの異世界から来た読書好きの一般人だとわかれば、どんな対応をしてくるかわからない。
だから、ルドウィンは怖くて、黙ってしまった。
「ああ。すまないな。誰しも、秘密の1つや2つ、言いたくないことの1つや2つあるからな。何も言う必要はない。わかっているさ。仲間だもんな。」
そう言ってリリアリーはガハハと笑った。
ルドウィンへの温かい気遣いが伝わってくる。
ルーナの時もそうだった。
もしかしたら、この仲間達だったら……いつか打ち明けられる時が来るかもしれないな。
ルドウィンはそう思った。
ルドウィンはリリアリーと別れ、次にティルシーのいる城に向かった。
一体どんなことをしたらこんな城で先生をできるのだろうか。
ルドウィンは疑問に思いながら、城の方向に向かって進んでいくと、城の門に看板があった。
『マスター・オブ・ハント・ティルシーズ・ロッジ』
物物しく書かれているが、つまり『ティルシーの狩猟教室』と同じ意味だ。
ルドウィンは、門番の人に自分がルドウィンであると、正体を明かし、ティルシーに会いたいと伝えると、門番の人が使用人を呼んできた。
その使用人が、ティルシーのところに案内してくれた。
豪華な内装の大広間にある、階段を登り、ティルシーの部屋の前に向かった。そして、使用人がノックし、こう言った。
「ティルシー様、会いたいと申しているものがおります。」
「なんにゃ?予約はいっぱいにゃよ。なぜ通したにゃ!」
「それが……ルドウィン様でございます。」
「にゃ!」
すると、ティルシーの部屋から何やらドタドタと足音が聞こえてきて……バタン!ドアが勢いよく開き、猫(ティルシー)が飛び込んできた。
「会いたかったにゃ!愛しのルドウィン!!」
抱きつくティルシー。
なんだ?どうした?何があった?
ルドウィンはティルシーをひっぺがすと、ティルシーがなぜこんなにルドウィンに懐いてるか、話してくれた。
なんでも、ルドウィンがあらゆる経済政策をしたおかげで、たくさんの鬼族の富裕層達が増えた。
優秀な鬼族の富裕層達は、会社を作り、社員を雇って、自分があまり働かなくても済むように半自動化する。
なので、お金と時間が有り余った富裕層達が、娯楽に、狩猟をするのだ。
狩猟の腕をもっと上達させるため、狩猟の腕がピカイチで、教え方も上手い、(ルドウィンはそう思わんが、鬼族からは評判らしい。)ティルシーの教室に依頼が殺到。儲けに儲け、この富で贅沢三昧。全ては、富裕層を増やしたルドウィンのおかげとルドウィンに懐いた。
これは予想できたことだ。
ルドウィンのいた世界の中世ヨーロッパでも、狩猟は王族や貴族の娯楽として親しまれていた。
その時代では、ティルシーのように、腕の良い狩猟の先生は、非常に高い地位にいた。
このことからもわかるように、狩猟は人気で、奥が深く、富裕層にとって絶好の娯楽になる。
だが、この世界の狩猟はルドウィンのいた世界の狩猟と一味違っていた。
まず、鬼族なら、小物ならすぐ捕まえられる。
なぜならその驚異的な脚力で獲物よりも素早く動けるからだ。
しかし、大物を捕まえるには、まず、大物を探さないといけない。
大物の場所を特定する専門的な技術が必要だ。
そして、特定しても、この世界でいう動物の大物は巨大で、力が桁外れに強く、もはや化け物だ。
まさに狩猟だ。
さまざまな知恵を使って、この猛獣を弱らせ、捕まえなければならない。
だから、鬼族にとって、最高の娯楽なのだろう。
ティルシーは小物の狩猟だけではなく、こういった伝説級の大物の狩猟も教えているらしい。
それが評判のポイントでもあると自信満々にルドウィンに説明してきた。
「ルドウィンになら、タダで、つきっきりで狩猟の奥深さを教えてもいいにゃよ」
今まで贅沢三昧して機嫌がとっても良いティルシーが、ゴロゴロ喉を鳴らしながらそう言った。
ふむ。
悪くない。
正直興味はある。
異世界転生する前はそのようなゲームもやり込んだことがあり、ゲームでも奥深かったので、現実ではもっと奥深いのだろう。
空いた時間に、ティルシーとルドウィン、2人でゆっくりと狩猟を楽しむのも良いかもな。
せっかくの善意だ。
ルドウィンは「いつか、一緒に狩猟に行けたら良いな」とゴロゴロ喉を鳴らしているティルシーの頭を撫でた。
ティルシーは、「嬉しいにゃ!」と目を瞑ってルドウィンに撫でられた。
その後、しばらくティルシーを撫でていると、時計が目に入った。
ルドウィンは、時間が思いのほか時間が過ぎていて、休憩時間を結構取ってしまったことに気づいた。
もう業務に戻らないとまずい。
ルドウィンはティルシーに「じゃあ仕事があるから、またな」と別れようとすると、「もっと構えにゃー」とティルシーがルドウィンを掴んで離さなくなった。
ルドウィンは困り果てていたが、使用人が「ティルシー様、ご飯の支度ができました」というと、あっさりご飯の方へ飛びつき、ルドウィンは告白してもいないのに、振られたような複雑な気持ちになった。
まあ、そんなところはティルシーらしい。
業務に戻るために、ティルシーの城から出ようとした時、慌てた様子の鬼族の部下が、ルドウィンを訪ねてきた。
「ルドウィン殿!探しましたよ!大変です!すぐ城に戻ってください!」
「どうした?」
「領主がルドウィン殿を呼べと言っているそうです!そして……領主の配下の軍に動きがあるとの報告が!」
「……」
ルドウィンはこの事態を予想していた。
そう。つまりこれは……。
「戦争になる恐れがあります!」
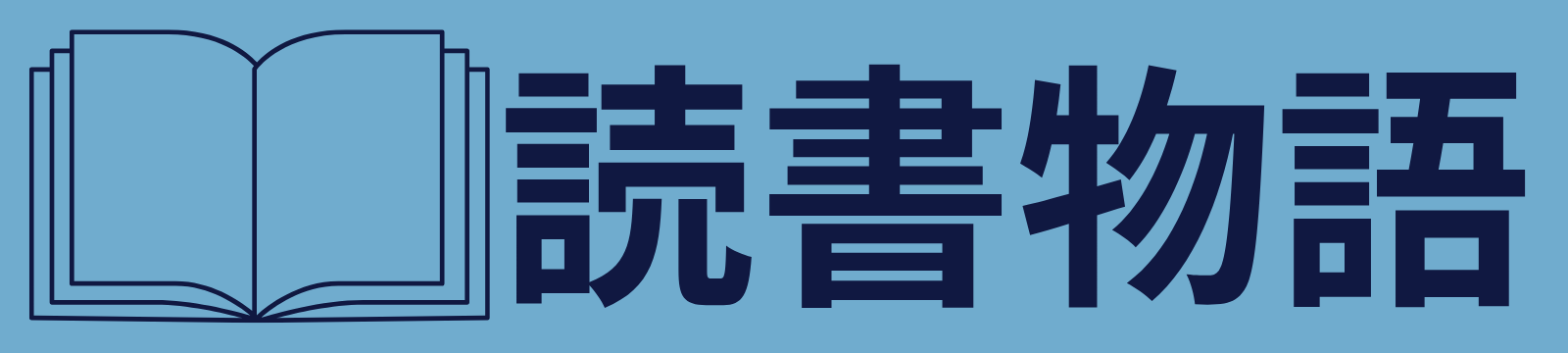









コメント