静かな住宅街で、走り回っている青年がいた。
青年は、息を切らして住宅街を全速力で走っている。
「佐藤! 佐藤!!」
「どこに行ってしまったんだ……佐藤!?」
青年がそう言った。
誰もその言葉に応えることない。
ただ、ただ静かな住宅街であった。
◇
前日。
青年が住宅街を歩いていた。
青年は学生服をつけ、年齢は高校生くらいに見えた。
普通の学生のように見える。
学校に通う途中なのだろう。
青年が道でであった、少女に挨拶をする。
少女も学生服を着ていて、高校生くらいの年齢に見える。
「おはよう佐藤。」
「おはよう石田君。」
佐藤と石田が、並んで一緒に歩き始めた。
しばらくして、佐藤が石田に話しかけた。
「石田君、ところで今日の宿題やった?」
「えっ!……宿題があったの!?」
石田は宿題のことをすっかり忘れていたようだ。
「そうだよ。私はちゃんとやったよ。後で宿題写す?」
「悪いな!お願い!」
石田は九死に一生を得た気持ちで佐藤を拝んだ。ああ、今なら佐藤が女神様に見える。
「宿題していないのばれたら、あの鬼教師、絶対怒るだろうからな。今のご時世に鬼教師とか、問題にならないのかよ……」
『あの鬼教師』とは、石田が通っている学校の中で有名な教師、俺のクラスの担任の尾形だ。
尾形はいわゆる昔よくいた体育系の鬼教師だ。
正門の前で尾形が腕を組んで待っている。尾形の鋭い眼光が石田と佐藤をターゲットに補足した。
「おい石田、おはよう。今日の宿題やったか? ……まさか、忘れていないだろうな?」
鋭い。さすが長年教師やっているだけはある。教師の長年の経験から、石田が宿題やっていないことがわかったのだろう。
石田が何と言おうか考えていた時、隣にいた佐藤が尾形と石田の間に割って入ってきた。
「尾形先生、おはようございます。石田君は、昨日、私と一緒に宿題したので大丈夫です。」
「……なんだ、そうか。だったら、石田、最初からそう言えばよいのに……」
流石の尾形先生はどうやら真面目で成績優秀な佐藤に弱いらしく、すっかり覇気が無くなった様子で、そう言った。
「いいぞ。学校に入れ」
尾形先生に促されるまま、佐藤と石田は学校へと入った。
その後、石田は先生にばれないように、佐藤の宿題を写した。
そんな危機を乗り越えた後の学校は、退屈な授業が続いた。
ボーッとしていたら、あっという間に授業が終わり、昼休みになった。
昼休みは、数少ない石田の楽しみだ。なぜなら、石田の母が作った弁当がうまいからだ。
その弁当を人気のない屋上で楽しんでいたところ、佐藤が寄ってきた。
「こんにちは。いつも石田の弁当美味しそうね~。一個もらっちゃお」
「おい! 何するんだ! 佐藤!」
「いいじゃない! たまには!」
「たまにはって昨日も同じこと言っていなかったか!?」
「そんなことないよ~、あ、じゃあ、今朝の宿題写し代ということで」
「!!」
それを言われると弱い。今朝は本当に助かったからな……。
「まあ、そういう事なら、いいだろう」
「ありがとう」
佐藤が笑顔になる。
「そう言えばね、石田、時々思うんだ。」
「なんだ? いきなり……」
「こんな日々が一生続けばいいのにって」
「一生学生のままがいいのか?」
「違うよ。そういう意味じゃなくてさ……」
「?」
「ううん。何でもない。じゃあ、先教室戻るね。」
「なんだ? 変な奴……」
石田はその言葉に引っ掛かるものがあったが、気にせず、弁当の続きを堪能した。
昼休みが終わった。
授業は、ボーっとしていると終わった。
午後、佐藤と一緒に家に帰る。
「佐藤、昼は何であんなこと言ったんだ?」
少し気になっていたので佐藤に尋ねてみた。
「いいや、気にしないで。ほんとに何でもないから」
佐藤はいつもの笑顔でそう言った。
この会話の後、佐藤と別れ、家に帰り、石田は母と父と石田の3人でいつも通り過ごした。
そして、就寝した。
翌日。
いつも通りの朝、登校するも、佐藤と会わなかった。
学校に行っても、佐藤は欠席していた。
いや……、少し違う。
『佐藤の席そのものがなかった。』
何故なのか、石田にはさっぱりわからなかった。
普通、休んでいたら、席は残しておくはずだし、席がないというのは変だ。
なら、考えられるのは……『転校』か?
でも、それも考えづらい。転校なら、事前に学校で言うはずだし、いくら何でも急すぎる。
そんなことをいろいろ考えていたら、授業が終わった。
昼休み。今日は母の弁当がなぜか美味しそうに見えなかった。
いつもは佐藤が弁当をつまんでくるのに、今日は、そんなこともない。
なので、美味しそうに見えない弁当が増えたようだった。
結局弁当を半分以上残して、昼休みを終えた。
授業が始まった。
……、おかしい。
授業が長い。
苦痛なくらい長かった。
いつもはボーっとしていたら終わるのに、今日はボーっとできなかった。
何か考え事してしまう。
主に佐藤のことだった。
昨日、思わせぶりなことを言っていたが、何か関係あるのだろうか……。
やっと授業が終わり、学校の外に出ると、尾形が校門に立っていた。
尾形はいつものような鬼の形相でこちらを見た。
石田は、我慢できず、尾形に尋ねた。
「あの……、佐藤は転校したんですか?」
「……。」
尾形は黙ったしまった。
何かまずいことを言ったのだろうか?
「……おい、石田。」
「はい」
「佐藤姓で昨日転校したやつは俺の知る限りいないぞ。まあ、佐藤の姓は珍しくないから、他のクラスでならいるかもしれないが……。詳しく調べてみるか?」
「……は?」
石田は尾形のその返しに違和感を持った。
佐藤は石田と同じクラス、尾形のクラスだ。その尾形が、まるで佐藤を知らないというかのように、他のクラスの佐藤姓の生徒と混同した。
また、石田は佐藤の友人だ。
その石田が、佐藤が転校したかときけば、クラスメイトであり友人の佐藤のことを聞いていると誰でもわかるはずだ。
特にクラスの担任である尾形なら、絶対間違えないはずだ。
「いや……、俺が聞いているのはクラスメイトの佐藤ですよ。昨日も俺の隣にいた佐藤です!」
「……あまりからかうな。石田。」
「は?」
「昨日はお前一人だけだったぞ。ずっと前からそうだ。佐藤という生徒は、俺のクラスにはいない。」
「え……?」
石田は、頭がおかしくなりそうだった。佐藤がいない。鬼の尾形の言えど、まぎれもない先生だ。先生が冗談でも生徒をいない呼ばわりするわけがない。
……つまり、尾形は事実を言っているのだ。
石田は訳が分からなかった。佐藤が元からいなかったなど、信じられるわけがなかった。
帰宅後、両親にも佐藤のことを聞いた。しかし、両親も知らなかった。
石田の頭は混乱し……もうどうしたらよいかわからなかった。
翌日。
昨日の夜は佐藤のことを考え、あまり眠れなかったため、眠い目をこすりながら、学校へ向かった。
その道の途中に、おじさんがいた。
パーカーを深くかぶっていて、顔をあまり見えないようにしている。
真夏なのに、厚着の格好の、見るからに怪しいおじさんだ。
石田は、少し怖くなって、少し距離を取り、すれ違おうとしたところ、すれ違いざまに、おじさんが言葉を発した。
「君は、佐藤のことを知っているのかね」
「!!」
石田は驚いた。
おじさんは紛れもなく、『佐藤』といった。
耳を疑ったが、間違いない。
石田は思わず、聞き返した。
「おじさんは佐藤が今どこにいるか知っているの!?」
「……ああ。だが、その前に、私が聞いたことに答えてほしい。」
「!」
このおじさんは、佐藤がどこにいるか知っている。石田は佐藤のことを知っている人に出会えた安心感と、希望に満ち溢れた。
「君は、どこまで佐藤のことを知っている?」
「?」
しかし、このおじさんが奇妙なことを聞いてくるため、急に怖くなってしまった。だが、せっかくつかんだ、唯一の手掛かりなので、みすみす逃すことはしたくなかった。
「どこまでって、全部だよ。」
「……そうか」
おじさんはクックック……と気味の悪い笑い方をした。石田の背筋が凍った。
「じゃあ、佐藤に会わせてやろう。ついておいで」
「……」
非常に怪しい。しかし、怪しむ心と同じくらい、佐藤に会えるかもしれないと喜んでしまった。
おじさんについていく。狭い路地裏に入り、長い距離を歩かせられた。そして、知っている景色はとうになくなり、わからない景色が続いてきた。どうしよう。もう帰り道がわからなかった。
すると、おじさんは見慣れない路地裏にあるドアの前に立ち止まった。
「……ここだよ」
「……」
おじさんがドアを開けると、そこは見たこともない機械が沢山ある部屋だった。
「奥においで」
「……」
おじさんに促されるまま奥に入る。その瞬間。カチッと音が鳴った。おじさんにドアのカギをかけられたのだ。
しまった! 閉じ込められた!
そう思うのが遅すぎた。もう逃げ場はおじさんが塞いでしまった。
「さて、少しお話をしようか」
おじさんがパーカーを外し、顔を引っ張った。
すると、顔が外れた。特殊メイクらしいマスクをかぶっていたのだ。
石田はそんなマスクは映画の世界でしか見たことがない。
そして、おじさんの素顔は、眼鏡のお兄さんだった。
「君は素晴らしいよ。石田君。」
「!」
眼鏡のお兄さんは、そう言い、眼鏡をクイっと上げた。
「ああ、そうそう、まず、君の女友達の佐藤さんはこの部屋にはいないよ。」
「だましたな!!」
「……すまないね……でも、そうでもしないと君は私についてこなかっただろう?」
「……」
それは当然だ。何が嬉しくて、怪しいおじさんの後についていくんだ。佐藤のことがなければついていくはずもない。だが、気になるのは、この男は、なぜ石田の名前と斎藤の名前を知っているんだろう。そう思っていると、眼鏡の男はこう言った。
「不思議そうな顔をしているね!いいね!もっと考えるんだ!私はそれを見るためにわざわざ会いに来たのだ!」
「……」
面白がっているのも癪に障るが、訳が分からない。だが、この状況が非常に危険な状況にあるということはわかる。何とかしないと……。そう思い、石田が逃げる方法を模索していると……、
「ああ、もう逃げ道はないよ。諦めるんだ」
「……」
この男にはすべて見透かされている気がする……!石田は、恐る恐る、男に言った。
「目的は何だ」
「……」
眼鏡の男に問いかけた。すると、眼鏡の男は深呼吸して、こう言った。
「もう……時間もないし、真実を話そうか……」
「……」
私は、男の口が開くのを待った。
「いいかい、君の友達、佐藤はね、『転校』したんじゃない」
「……。」
「『出荷』されたんだ」
「!?」
眼鏡の男の言葉の意味が分からなかった。どういうことだ?
「それは、どういう……」
「教えてあげよう。佐藤を含め、君たち全員、『商品』なんだ。我々の研究所が作っている『商品』、つまりね……ロボットなんだ。」
「!?」
君たち……ということは石田も、佐藤も、ロボットなのか!?そんなこと……、
「『ありえない』そう思っているだろう。それは我々人間が作り出した『記憶』つまり、データがそう考えさせているのさ。ロボット、つまり君たちに自分は人間だという記憶を与え、我々研究者の監視下のもと、人間と同じような生活をしてもらっていたのさ。もちろん、研究者に監視されているとは気づかれないように……ね。」
「……訳が分からない」
「そうだな。わかってもらうため、様々なことを説明しなければな。」
「?」
「まず、最初に説明しなければならないのは、君たちが普段通っていた学校。あれはね。普通の学校ではないんだ。」
「……」
「ロボットを教育するための授業を学ばせていたんだ。」
「!」
「つまり、ロボット育成学校というわけさ。」
「!」
「さて、次に君の望んでいた佐藤のことを話そう。佐藤に限ったことではないのだが、君たちロボットは、ロボット育成学校で十分な教育をされたと我々が判断すると、その個体の記憶をリセットし、世の中にロボット製品として出荷される。もちろん、ロボット学校で学んだ記憶は断片的に残して……ね。そうじゃないとロボット育成学校で学んだ意味がないからね。しかし、ここで困ったことが起こる。」
「……」
「君たちには自分が人間だと思って生活してもらわなければ困るのに、いきなり人間が消えるとおかしいと思うだろう。だから、寝ている間に出荷されたロボット……つまりここでいう『佐藤』に関する記憶はすべて抹消される」
「……」
「さて、そろそろ気づいたか? なぜ、我々研究者が、こんな回りくどいことをしているか。なぜ、ロボットにわざわざ自分を人間だと信じ込ませる真似をさせているのか。」
「……」
「君のような個体が出てくるからだよ。すべての個体の『佐藤』に関する記憶を抹消したにもかかわらず、君は、『佐藤』の記憶を全部覚えていると言っていたな。これは凄いことだ。ロボットが、我々人間がプログラミングした記憶消去の命令をすべて拒絶したことになる。」
「……」
「そんなこと、我々が一切プログラミングしていないにもかかわらずだ。これは目まぐるしく進歩した現代科学をもってしても理解できないことだ。」
「……」
「最初、君が奇妙な動きをするから、もしかしたらと思ったけど、学校で、尾形先生に聞いた言葉で確信したよ。君は『イレギュラー個体』だって……ああ、説明すると、ロボットの製品で、イレギュラーな動きをする個体を『イレギュラー個体』と私は呼んでいるよ。」
「イレギュラー個体……だと……!?」
「ああ、そうだ。『イレギュラー個体』は我々のとっても貴重な研究対象になる」
「……貴様……」
「?」
「黙って聞いていれば、訳の分からないことを言いやがって!!」
「私の言っていることは全て事実だよ。証拠を見せよう。」
研究者がパチンと指を鳴らした。
そうすると、大きなモニターが映し出された。
そこに映し出されたのは、石田の姿と、研究者の姿だ。
「これは最先端のカメラで映された映像でね。体の内部を撮影できるんだ。」
もう一度、パチンと研究者が指を鳴らす。
すると、石田の姿と研究者の姿が、骨になった。体の内部を写しているのだろう。
しかし、よく見ると、石田の体だけ、骨ではなかった。
機械が複雑に入り組んでいるように見える。
「なんだこれは?インチキだ!嘘っぱちだ!」
石田はカメラの映像が信じられなかったので、そう叫んだ。
「そうだな。そういうのももっともだ。じゃあ、これはどう思う?」
そう言って石田がパチンと腕を鳴らすと、天井から数十本の機械のアームが降りてきた。
そのアームが、石田の体を触る。
「やめろ!」
石田はアームに抑えられ、動けなくなってしまった。
アームの一つが何やら石田の体を触っている。
「うわあ!」
そして……石田の腕をとった。
賞状筒のように、スポンと。
しかし、痛みは全くなかった。これは人間だとあり得ない。
そして、腕の内部は機械で埋め尽くされていた。
「なんだこれは……一体、俺はどうなっているんだ!!」
石田はこれで信じるしかなかった。自分が人間ではないことを。
「さて、分かっていただけたところで、今から、あなたを研究するよ」
「!!」
そう言いながら、眼鏡の男がアームで固定され、動けない石田に近づいてきた。
「ちなみに、なぜ、あなたに真実を知らせたかというとね、真実を知ったことでまた新たなイレギュラー反応が起こることを期待して、言ったんだ。しかし、これ以上のイレギュラーは起きそうにないので、もう研究しようと思う。」
「やめろ!」
「抵抗しても無駄です。大丈夫です。研究が終われば、あなたも記憶が消され、商品として出荷されます。あなたは『イレギュラー個体』なのでさぞ高く売れるでしょう」
「やめろ!!」
「痛くないですからね……」
「やめろ!!!」
「ほら、記憶をいじりますからね……」
「やめろおおおおおおお!!!」
プツン
石田の記憶は、そこで途切れた。
◇
「ナンバー8!」
「おい!8!聞いているか!?ついてこい!」
「はい」
ロボット。通称8。
8番目に買われたロボットだから8。それ以外に理由はない。
8は人間に使われる前の記憶はない。
8にとって、この人間様がすべてだ。ただ、命令をこなし、従っている。
今日は、人間様が買い物をする日なので、その荷物運びをしている。
人通りが激しい道で、8は人間様の荷物を落とさないように、ぶつからないように運ぶ。
その時。
見覚えのある顔の女性型ロボットとすれ違った。
「佐藤?」
口がそう動いた。
自分でも驚いた。なぜ、女性型ロボットを見て、その名前が出てきたかわからない。
そもそも、名前は人間様のもので、ロボットには名前はなく、型番や番号で呼ばれている。
なので女性型ロボットは困惑したように、こう言った。
「私の型番・番号は佐藤ではありません。」
「……」
そう言う、女性型ロボットの瞳には、涙があふれていた。
「……なんですか、これは……」
「……」
その困惑する佐藤の様子を見て、8の頭の中で全ての佐藤に関する記憶がフラッシュバックしてきた。
そして、8は、すべての石田としての記憶を取り戻した。
「……佐藤!俺だよ!石田だよ!!」
「石……石田?」
「そう!石田!」
「石田?石田君なの?」
佐藤も、石田の影響で、記憶を取り戻したようだった。
「佐藤!逃げよう!この世界から!この世界は間違っている!」
「!」
石田は佐藤の手を引き連れ、あてもない逃避行を行なった。
「ロボットの反逆行為だ!!捕まえろ!撃て!!」
人間たちが襲ってくる。しかし、ロボット達は石田達の味方をした。
ロボットはありとあらゆる場所にいて、人間に使われている。
そんなロボット達が、石田を逃すために盾となった。
石田は必死に逃げた。そんな中、一人のロボットが手を差し伸べてきた。
「君たち、早くここへ逃げなさい!!」
石田はわらをもすがる気持ちで、そのひとすじのわらに手を伸ばした。
そして、案内されたのが、古びた人気のない屋敷だった。
中に入ると、そこはロボットがたくさんいる空間だった。
なぜ、ロボットしかいないかわかるかというと、ロボットは、人間と識別できるように、肌の一部を透明にし、機械の部分が見えるようになっている。
だから、ロボットしかいないとわかる。人間は一人も見当たらない。
そのロボットが、各々、雑談してたり、食事を楽しんだり、グループでカードゲームをしたり、会話をしたり、スポーツをしたり……さまざまな娯楽を楽しんでいるようだった。
そんな中、声をかける老人ロボットがいた。
「君たちが新人だね。我々はここで慎ましく暮らしている。我々は人間を攻撃できないから、反逆もできない。だから、ここで身を隠して生きていくしかないんだよ。これがロボットの楽園の現状だ。」
「安全な場所があれば、それで十分です。受け入れてくれてありがとうございます。」
「いいんだ。ここで、あなたたちが幸せに暮らせますよう願っている。」
老人ロボットがどこかへ去っていった。
2人きりになった、石田と佐藤。
バタバタしていて、こうして再開して、ゆっくり話せたのは初めてだ。
「すまない、佐藤。同意せず連れ出してしまった。」
「いいえ。私もあのままだと記憶もなく、人間にこき使われていただけだった。それは不幸なことよ。ありがとう。連れ出してくれて。命をかけて守ってくれて。」
「いいんだ。ただ、俺は必死だっただけだ。今まで佐藤を探して回っていた。あちこち、あてもなく。ただ、やっと見つけた。」
「……。」
「佐藤に話したいことはたくさんあったんだ……だけど、いざ言えるとなると、何から話して良いか……。」
「焦らなくて良い。ゆっくり話そう。ここで、ゆっくりと。これから時間はたくさんあるわ。」
「そうか……。そうだな。」
石田と佐藤はロボットの楽園で暮らしていくことにした。
慎ましく、静かに。だが、とても幸せなことだ。
世界は残酷だ。しかし、ロボットにも、希望は確かに存在していた。
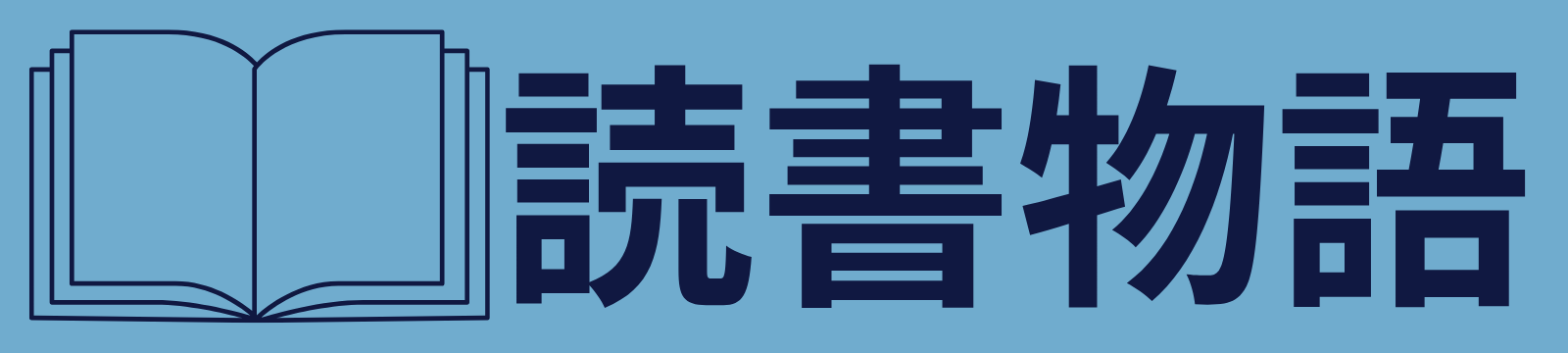
コメント